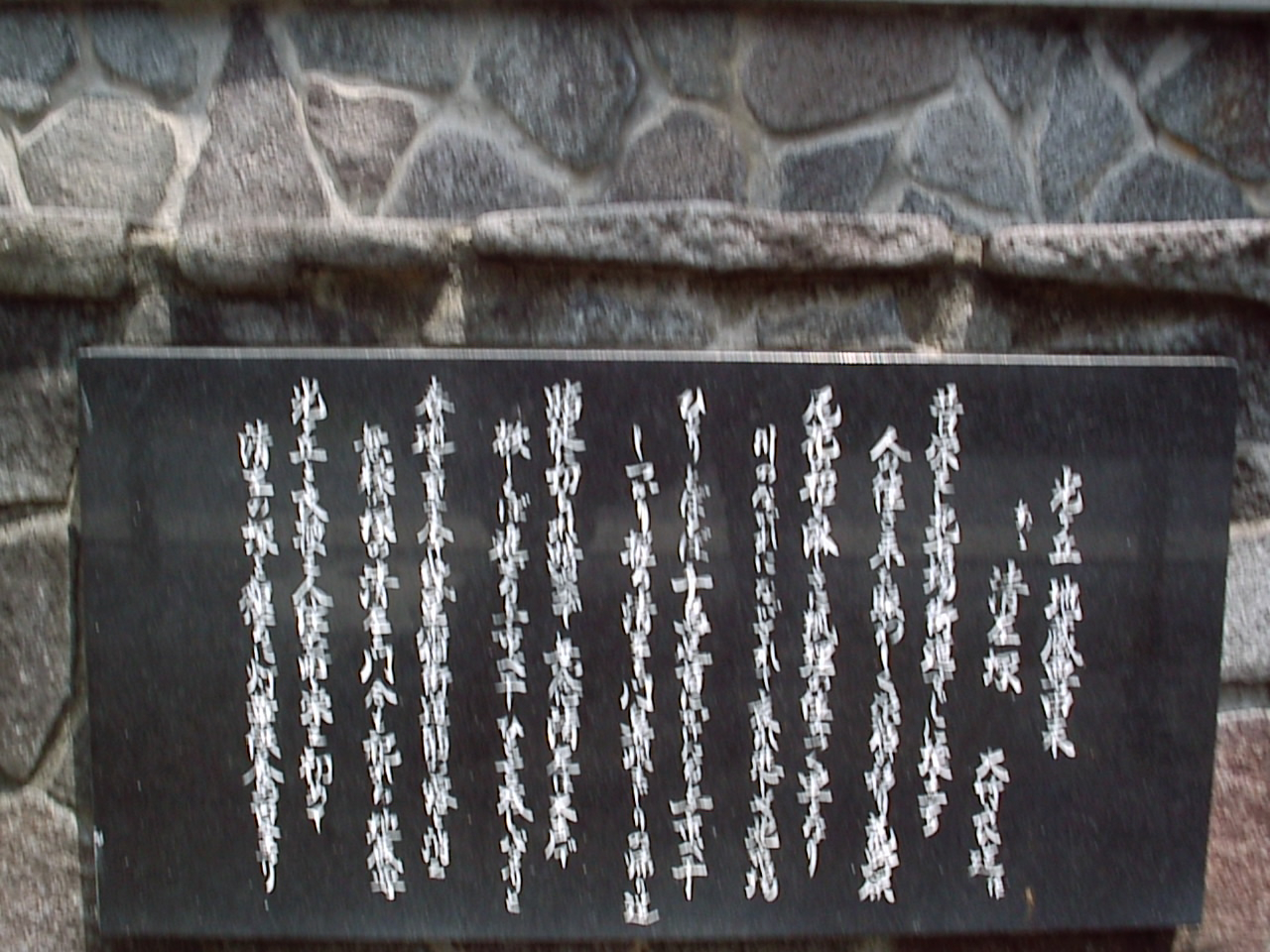ニュース
2022/03/11 TGR光が丘今昔
TGR光が丘今昔69 「岐阜県多治見市光ヶ丘一丁目~五丁目」
岐阜県多治見市光ヶ丘一丁目~五丁目
① 正式住居表示(町名) 岐阜県多治見市光ヶ丘一丁目~五丁目
② 施行年月日 昭和37年 5月 1日施行 町名地番変更
③ 施行前の旧町名 岐阜県多治見市大字野中字北市場,大字野中字坂井戸,大字野中字一ノ井,大字野中字田島,大字長瀬中之郷入会字北市場,大字大原字東田,大字中之郷字西坂,大字中之郷字五輪坂
④ 現在の主たる地目 宅地,-商業地と住宅の混在地域
⑤ 町名(名称)決定した主たる理由
不明です。(人伝えで定かではありませんが,公募により地域で決定したとの情報がありました。)
⑥ 候補となった他の町名の例示
不明です。
⑦ 歴史的なものなど何か貴所「光が丘,光ヶ丘 等」で由緒あるもの
由緒あるものについては,特にありません。光ヶ丘地蔵と呼ばれる地蔵かどうかは,分かりませんが,光ヶ丘地内に2体の石仏がございます。別添資料をご覧下さい。
⑧ 「が,ヶ,ガ」を使用した理由
不明です。
⑨ その他特記事項
特記事項なし。
岐阜県多治見市光ヶ丘は,岐阜県多治見市西部にあり,JR多治見駅から徒歩20分位のところにある。近くには,中央自動車道多治見ICがあり,宅地ではあるが,幹線道が通り商業地域もある。光ヶ丘一丁目には,石仏があり,代表的なものは境地蔵,もう一体は「光ヶ丘地蔵尊」と呼ばれている。境地蔵については,多治見市史に拠れば,次のような記述がある。
「境地蔵
地蔵はこの世と地獄の境にたって,地蔵におとされる死者を救うというが,一方では境の神,さへの神(塞の神・妻の神)と習合して村はずれや峠,辻などにもたてられることが多い。童謡にも「村はずれのお地蔵さんは」とうたわれている。塞の神とは悪魔や不幸が村に入ってこないように,道をふさぐ神のことである。
現在の若松町と光ヶ丘の境にたつこの地蔵は,通称境地蔵と呼ばれている。その顔はほほえみをたたえていかにもやさしい。右手に錫杖を持ち,左手に宝珠を捧げた延命地蔵である。右側に「寛政九(1797)丁巳三月日」左側に「長瀬村中野江村」と刻まれている。「中野江村」は「中之郷村」で境地蔵といわれるごとく,長瀬村と中之郷村の境に立つ地蔵であった。石仏の大きさは,幅43[cm],高さ84[cm]である。」(多治見市役所;不明)
一方,光ヶ丘地蔵尊は,直接筆者が実地踏査した結果,次のようなことが分かった。
光ヶ丘地蔵尊
この地蔵も,光ヶ丘一丁目の光ヶ丘公民館脇に光ヶ丘第一町内自治会によって奉納されている南無地蔵菩薩である。石仏の大きさは,幅26[cm],高さ56[cm]で,境地蔵より一回り小さい。右側に「嘉永五子年」,左側に「為正月廿四日仏」とあり,下側に「久保原村松村銀蔵施主タジミ村加藤伊左衛門」とある。台座には,大竹良造作による「光ヶ丘地蔵尊由来」が大字野中字北市場の北市場街道が栄えていた頃からのものであることが述べられている。