-
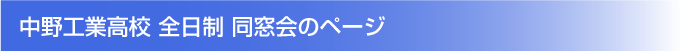

-
卒業生による講演会 第5回

卒業後の歩み
10M 梅田 清永
(H22.12.24)
私は、昭和15(1940)年、東京都杉並区に生まれ、同 区立の中学校を卒業し昭和31(1956)年4月、都立中野工業高校の機械科に入学した。同34(1959)年3月機械科卒業、同年4月 萱場(カヤバ)工業株式会社(現 KYB株式会社)に入社した。
1.就職先を選ぶ時のひとつの考え方について
高卒の就職内定率が厳しい状況の中である昨今、就職先を選ぶ時、色々な条件の中で、ひとつの考え方について提案するので参考になれば幸いと思う。
・企業が大きい、・給料が高い、だけで評価してはいならない。
(1)中小企業でも、「これから会社が伸びそうだ」 と言うことも見ながら
(2)自分の実力にあっているのか
(3)自分の学んだことが企業で役立てることが出来るのか
(4)自分がその企業でやることが世の中に役立つ可能性はあるか
等を考える。
就職ができたならば、就職したならば、そこで努力し、ある程度は我慢して耐えること⇒『努力・忍耐』・・これは、何にでも共通することだ。
私はこのような考えに基づき就職先を選んだ。
⇒中小企業・・自分の波長(考え)と波(企業の方針)が合えば、多くの経験といい仕事:社会の役に立つ実績が残せる。
2.萱場工業株式会社に入社してから
昭和34(1956)年 入社時の会社状況
(1) 業種:輸送機器(自動車のショックアブソーバー等)油圧機器の製造
(2) 資本金:3,800万円
(3) 従業員数:約800人
(4) 試用期間:6ヶ月・給料:7,600円/月⇒本採用後 給料:8,600/月
その年(昭和34年:1959)大学を受験したが入試に落ちた。
3月下旬から正式入社に先駆け、会社の見習い実習が始まった。入社式は4月1日にあり配属先が技術部研究課となったが、私自身は工場の生産現場を経験してから間接部門に進みたかった。いきなり技術部研究課に配属となりおどろいた。
4月1日から、大卒新入社員と一緒に三ヶ月間は、午前中:実習・研修、午後:職場に戻って勉強となった。実習・研修を終了し、正式に職場に配属になり、最初の仕事は先輩研究員の助手で、実験治具の製図・設計の手伝いであった。仕事が慣れてくるに従い、実験の手伝い、簡単な実験治具の設計を任されるようになった。就職して1年後、新入社員が実習・研修に来た際に、研修の一部を担当するようになった。
就職して2年目の昭和36(1961)年2月、会社から歩いて通える芝浦工業大学の機械工学科2部(5年制)を受験し、やっと合格した。
大学の機械工学部を卒業後、これからは電子技術も必要になると考え、東京電機大学電気学校(夜間の専門学校:2年制)電子科に入学し、卒業した。
昭和45(1970)年 浜松町の研究所が神奈川県相模原市に移転したため、毎朝5:30に起床し、杉並の自宅から相模研究所へ通勤した。
相模研究所では
(1)国鉄技術研究所と協働で貨車操車場入れ替え作業の自動化機器の研究開発:実用化に成功し、高崎、郡山貨車操車場などに設備されたが、国鉄の貨物輸送方針の変更でやがて廃止となった。
(2)海洋開発の先駆け:水中マニピュレータの開発や深海マンガン団塊の採取実験などの開発に参加した。
*その頃、出版社から技術論文の寄稿を依頼され、投稿した⇒水中マニプレータ:油圧技術(日刊工業)、ロボット(日本ロボット工業会)
3.研究所から工場 設計部プロジェクトティーム へ転勤
研究所と工場設計との大きな違いは、設計図面の納期・コスト(採算性)の厳しさである。考えれば当たり前ではあるが、再認識させられた。
工場の設計プロジェクトでは
・潜水艦救難母艦:水中油圧装置の設計及びラムテンショナの基本設計
・補 給 艦:洋上補給装置用油圧装置の基本設計⇒生産設計・・三重工場へ単身赴任・・幹部昇格
・補給艦『とわだ』『はまな』『ときわ』の3艦の洋上装置、艦内移送装置の主任設計課長となった。
・『洋上補給装置』、『艦内移送装置』とはどんなもの・・補給艦に装備され、PKO絡みの一環としてインド洋上で同盟国艦艇に、油・物資を補給するための装置。
4.工場から営業部へ転勤
平成元年6月 設計技術を武器に、東京の営業へ転勤となり、海上自衛隊、艦船を建造する造船所へ多くの装置の提案・売り込みを行った。私が航空機器事業部と連携してプレゼンテーションしたシステム装置『航空機タイヤ組み立て装置』が航空自衛隊百里基地、千歳基地を始め、多くの航空基地に採用された。
平成12年9月 60歳で定年したが、同年10月 引き続きカヤバ工業株式会社に常勤嘱託で再就職し営業部長補佐として勤務し、平成16年3月、退職した。その年の8月 ハローワークの紹介で病院にパートの営繕係:何でも直し屋、として就職し、平成20年3月 病院が閉院となったため解雇となった。
病院に就職中に地域の町会より推薦候補となり、杉並区より推薦され、平成17年7月 厚生労働大臣より東京都民生委員児童委員の委嘱を受けた。現在地域福祉の向上の一翼を担い、ボランティアとして活動中である。 以上
-
