
本日、「科学の祭典」(研究発表会・表彰式)が東京ビッグサイト国際会議場で開催され、本校の生徒も参加しました。
ポスター発表では、5年生の生徒が「音楽における 1/f ゆらぎがもたらすリラックス効果」という内容で発表しました。これは4年生の時から続けていたライフワークプロジェクトで取り組んできた内容です。発表しているポスターの前には絶えず聴衆が訪れ、活発な議論をしていたのが印象的でした。
プレゼンテーション発表では、別の5年生の生徒が「濡れた紙が乾いたときの凹凸は防げるのか?」という内容を英語で発表しました。首都大学東京の先生方のサポートで電子顕微鏡も使わせていただき、充実した内容でした。今までの研究成果をまとめ、分かりやすい英語での発表になっていました。なお、この研究発表会でプレゼンテーションを実施したのは、理数リーディング校としての取組みの一環となります。
その後、後期課程(高校)の生徒を対象とした「科学の甲子園 東京都大会」の結果発表がありました。今年度は、残念ながら表彰されることはありませんでした。今後はさらに健闘することを願っています。
その後の表彰式では、前期課程(中学)の科学部が参加した「中学生科学コンテスト」が受賞した優秀賞(実技I部門)の表彰がありました。詳しくはこちらを御覧ください。
|
|
|
|
|
|
本日、千葉県文化会館大ホールにて「第8回日本学校合奏コンクール2019 全国大会グランドコンテスト」が開催されました。 南多摩フィルハーモニー部は、5年連続の出場となり、今年度はドヴォルザーク作曲「交響曲第3番より第3楽章」を演奏し、銀賞をいただくことができました。金賞をとることは叶わず悔しい思いもありましたが、全国大会という舞台で楽しんで演奏できたことや、お客様からたくさんの拍手をいただけたことを誇りに思っています。
雨の中、遅い時間にも関わらず、遠方まで応援に来てくださった保護者の皆さま、OGの皆さま、本当にありがとうございました!
|
|
|
本日午後、1年生は、ひの煉瓦ホール(日野市民会館)で開催された「日本の伝統芸能鑑賞教室」で狂言を鑑賞しました。
人間国宝 野村万作氏と息子の野村萬斎氏の共演で、演目は「附子(ぶす)」と「茸(くさびら)」。「附子」は、主人が太郎冠者と次郎冠者に留守番を言いつけ、桶の中に附子という猛毒が入っているから近づかないように言い残して立ち去るが、実は中身は砂糖で、それを全部食べてしまった二人の、主人へのユーモラスな言い訳に会場では笑いがおこりました。「茸」では、笠をかぶり面をつけた茸たちのユーモラスな所作に何度もどよめきが起こりました。
冷たい雨が降る日でしたが、生徒たちは普段なかなか見ることができない狂言を大いに楽しんだ様子でした。
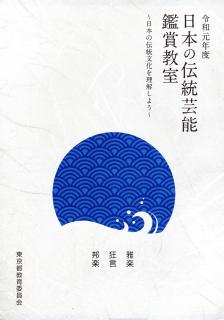
本日午後、中学生の「税についての作文」表彰式が、八王子東急スクエアにて行われました。八王子市内から3,749通の応募がありましたが、本校3年生の7名(うち1名は欠席)が表彰されました。
税の作文とは、将来を担う中学生が、身近に感じた税に関すること、学校で学んだ税に関すること、テレビや新聞などで知った税の話などを題材とした作文を書くことで、税について関心を持ち、正しい理解を深めるという趣旨で実施しているものです。
本日の表彰式では、本校3年生の代表生徒が、中学生の医療費負担が軽減されていることについての作文を朗読し、会場から盛大な拍手をいただきました。
本校では、毎年、3年生を対象に税の作文への応募を行っています。税という言葉を聞くと、「取られる」というイメージをもつ生徒が少なくありませんが、私達が健康で文化的な生活を送るために必要なサービスは、国民から集めた税金によってまかなわれています。生徒の皆さんには、税の作文を書くことを通じて、税の大切さについて再認識してほしいと思います。
|
|
|
本校の2年生が「第63回東京都児童生徒発明くふう展」において、見事に入選しました。受賞作品は「偏光板 mail box」。本年12月5日(木)から7日(土)まで、東京国際フォーラム ガラス棟 ロビーギャラリーに展示されます。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。詳しくはこちら(東京都産業労働局の報道発表資料)を御覧ください。
本日午後、4年生を対象とした進路講演会「先輩に学ぶ」を実施しました。この進路講演会は、先輩である卒業生の生き方を学ぶことで、自己の生き方・在り方を考えることを目的としています。今回の講師は、現在、総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 博士課程に所属し、第60次日本南極地域観測隊にも参加していた和田智竹氏にお願いしました。講演テーマは「極限環境【南極】で暮らす知られざる生物の生き様 ~北極、南極、世界のジャングルで見てきた素敵な自然の紹介~」でした。様々な珍しい生物の標本や写真を見せてもらいながらの講演で、今まで馴染みのなかった地域について色々と知ることができました。
以下に生徒の感想を紹介します。
|
|
|
文部科学省WWLコンソーシアム構築支援事業の管理機関である東京都教育委員会は、Diverse Link Tokyo Edu という学校と社会・世界をつなぐ東京都独自の学びのプラットフォームを構築する事業に取り組んでいます。その事業の一環として、オーストラリア・クイーンズランド州政府、クイーンズランド工科大学及び東京大学先端科学技術研究センターによる特別講座が開催されました。使用言語は全て英語でした。
第1部は、東京大学先端科学技術研究センター教授 杉山 正和 氏、クイーンズランド工科大学教授 Ian Mackinnon 氏による講演が行われました。テーマは、再生可能エネルギーに関する最新の日本の取組と世界の動向、国際連携の重要性及び、実験の実演により、太陽光と水素とがどのように発電に関係するのかというものでした。第2部は、本校の5年生の生徒による水素についての研究発表でした。発表直前に特別ゲストとして小池百合子都知事が出席されました。知事の前で英語でプレゼンテーションできる機会を得て、とても光栄なことでした。生徒は堂々と発表し、発表後の質問にも流ちょうな英語で答え、周囲から称賛されました。
今後も様々な機会で生徒発表の場を作り、探究活動を発展させていきたいと思っています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本日、東京都中学校駅伝競走大会が、板橋区立荒川戸田橋陸上競技場前をスタート・ゴールとする荒川河川敷特設コースで開催されました。男子(6区間・18km)は参加117校中15位になり、女子(5区間・12km)は参加115校中4位になり入賞しました。この結果、女子は、11月30日(土)・12月1日(日)に神奈川県横浜市で開催される関東中学校駅伝競走大会への出場が決まりました。
陸上競技部(前期)としては、女子だけでも4年連続、男女を含めると5年連続での関東駅伝への出場となります。おめでとうございました。関東駅伝での健闘をお祈りいたします。
|
|
|
|
本日は、1年生が「地域調査」、3年生が「科学調査」として、終日、フィールドワーク活動に取り組みました。この取り組みは、7月9日(火)に続いて2回目となります。1回目の活動以降、各クラスでの中間発表等を通じて、先生方や他の班のメンバーからの指摘も受けてきました。それらを参考にして考察を深め、さらに調査・研究を行うべく、本日は活動しました。
1年生は主に校外で、3年生は主に校内での活動でしたが、自分たちの班のテーマをより深めることができました。多くの方々にお世話になり、ありがとうございました。
今後は、今までの結果をまとめて考察をし、来年3月20日(金・春分の日)に開催される成果発表会で発表することになります。一年の集大成となりますので、しっかりと頑張りましょう。
以下の写真は、校内で実施した3年生の活動のひとコマになります。
|
|
|
|
|
|
|
|
本日午後、東京大学安田講堂で行われた「2019年コスモス国際賞受賞記念講演会」に、本校の6年生2名が参加しました。
講演者は、デューク大学のスチュアート・L ・ピム教授です。ピム教授は保全生態学の第一人者で、生物多様性の保全に対して科学と実践の両面において多大な功績を果たしています。進行する生物多様性の喪失に対して、私たちに何ができるのか? 課題は山積しているが、学生だからこそできることが沢山ある。悲観的になるよりも今すぐ行動すべきだ! という熱いメッセージをいただきました。
以下は、参加した生徒のコメントです。

本日、3年生が首都大学東京を訪問しました。本校では、後期課程における大学への進路意識を高める目的で、毎年11月に3年生を対象に実施しています。
午前中には、文理両方の分野の3つの講義を受講しました。その後のキャンパス見学では、牧野標本館や図書館などを首都大学東京の高大連携室の方々などの案内で見学させていただきました。昼食後には、本年度、取り組んでいる「科学的検証活動」の中間発表を各クラスの代表生徒が1班ずつ行い、多くの生徒や高大連携室の方々からの鋭い質問にもしっかり答えることができました。
少し肌寒い一日でしたが、大学での学問や大学の雰囲気に触れるには絶好の機会となったと思います。
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
本日午前、3年生は校外学習で、コニカミノルタ サイエンスドーム(八王子市子ども科学館)に行きました。
通常通りに登校した後、良い天気の中、浅川の河川敷を歩いて出かけました。サイエンスドームでは、展示室で遊びながら科学に触れたり、ISS(国際宇宙ステーション)でのミッションのシミュレーションに挑戦したり、八王子隕石やハチオウジゾウに関する展示を見たりしました。プラネタリウムでは、今、まさに理科(地学分野)で学習している内容の投影を見ました。
普段の学校の授業では体験できないことに触れる貴重な機会になったと思います。今後の理科の学習に役立てて欲しいものです。
|
|
|
|
|
|
本日、「科学の甲子園 東京都大会」が都立多摩科学技術高等学校で開催されました。本校からは、5年生の6名の生徒が筆記競技と実技競技に参加しました。
筆記競技は、2時間で物理・化学・生物・地学・数学・情報に関する問題にチーム全員で取り組みました。実技競技は、事前にテーマが公開されていて、自分たちで製作したターゲットマーカーと探査機を落下させ、落下体同士の距離(近距離が優位)と時間(差がある方が優位)を計る競技でした。校内で試作・テストを繰り返して作った設計図やメモを持ち込んで取り組みました。参加した生徒からは、「問題は難しかったけれどいい経験をした」という感想がありました。
本日の結果は、2週間後に開催される「科学の祭典」で発表されます。良い結果であることを祈っています。
|
|
|
|
本日午後、本校視聴覚室において都立中高一貫校生徒会交流会が開催されました。今年から都立中高一貫教育校の全校に参加を呼びかけました。当日は、白鴎・両国・桜修館・富士・大泉・南多摩・武蔵・三鷹の附属中学校および中等教育学校の前期課程の生徒会役員を中心とした48名が参加しました。
今年度は、第60回九州高等学校演劇研究大会 最優秀賞、第43回全国高等学校総合文化祭演劇研究大会 優秀賞(全国2位)を受賞した鹿児島県立屋久島高等学校の受賞作『ジョン・デンバーへの手紙』と映画『屋久島からの報告』を事前に鑑賞してもらい、当日は下の2つについて分科会形式で討論しました。
以下は、受賞作品を観た参加生徒の感想です。
以下は、生徒会として学校生活の中で実践できることについて、出た意見です。
最後のフリートークの時間には和気藹々と話が弾み、「もっと話していたい」という感想を多くの生徒が口にしていました。
準備をしていた生徒会役員のみなさん、ありがとうございました。来年度もよろしくお願いします。
|
|
|
|
|
|
||
本日の1・2限目、3年生による英語レシテーションコンテストを本校ランチルームにて行いました。
今年度は “I Have a Dream” と “Gon the Fox”(ごんぎつね) を題材に、それぞれクラス予選を勝ち抜いた上位16名が英語によるレシテーション(暗誦)を発表しました。司会は惜しくも本選を逃した生徒が務めました。声・発音・表現力・暗誦の4観点によって採点され、審査員は、JET2名と3年生の授業を担当していない英語科の教員が行いました。気持ちを込めたセリフ、表現豊かなジェスチャーなどに、大きな拍手がわきました。
本校では、1・2年生によるレシテーションコンテスト、3年生によるこのレシテーションコンテスト、4年生のオーストラリア語学研修旅行など、発達段階に応じた英語教育プログラムを丁寧に展開しています。
|
|
|
本日午後、3年生から5年生を対象に「EUがあなたの学校にやってくる」を実施しました。このプロジェクトは、駐日欧州連合(EU)代表部ならびにEU加盟国大使館の外交官が、日本各地でEUや自身の出身国について出張授業を行うものです。欧州連合(EU)加盟国の大使館員等から直接話を聞き、EUおよび日本とEUの関係をより身近に知ることを目的としています。今年は全国49の学校で実施されました。
本校には、駐日フランス大使であるローラン・ピック氏(Mr. Laurent PIC)が来られました。普段あまり聞きなれない美しいフランス語の響きで大使本人からお話を聞ける貴重な時間となり、日本とは異なるヨーロッパの視点からの世界観を学習する機会となりました。
以下に生徒の感想を紹介します。
|
|
|
 東京都立南多摩中等教育学校 Tokyo Metropolitan Minamitama Secondary Education School
東京都立南多摩中等教育学校 Tokyo Metropolitan Minamitama Secondary Education School