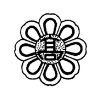ニュース
1.日程 2025年1月5日(日)~7日(火)
2.巡検場所 日本モンキーセンター(愛知県犬山市)1/5,6
針江 生水(しょうず)の郷(滋賀県高島市)1/6
国立民族学博物館(大阪府吹田市)1/7
3.参加生徒 15名 1年生 9名 2年生 4名 3年生 2名
4.内容及び生徒の感想等
【1/5(日) 内容】
初日は日本モンキーセンターにて,フクロテナガザル,アヌビスヒヒ,ジェフロイクモザル,ボリビアリスザルを観察しながら,それぞれの種の移動に関する習性(二足歩行をするか,四足歩行をするか/腕でぶら下がるか,尻尾でぶら下がるかなど)を観察しました.また,個体それぞれの四肢がどのようになっているのか観察し,図として記録しました.
その後,サルの体のつくりは,住んでいる環境や食性に大きく関わっていること,それらに適応して進化してきたことを、講義を通して学びました.



最後には,リーキー博士から西田利貞氏(霊長類学者/京都大学名誉教授)へ寄贈され,250万年前にホモハビリスが作ったとされるオルドワン石器(実物)に触らせてもらいました.

【生徒の感想】
・視点を決めて,実際にサルをそれぞれ見ていくと,種によってもっている特徴が多種多様であることに気付いた.尻尾をもっていたり,足よりも腕の方が圧倒的に大きい種がいたりするなど,特徴の違いが分かった.
・焚火を囲むヤクシマザルを見たが,若いサルは周りを見て焚火との距離感を保っているのか,好奇心から少し熱い思いをした経験もあるのかということが気になった.
・ヒトもサルもみんな進化してきた生き物であるということがわかり,ヒトだけが偉いなどというわけではなく,どの生き物も立場はみんな平等だと思った.
・サルの8割くらいがしっぽを使って生活していると思っていたが,違うことが分かった
・ゴリラ館にあったパネルに、ヒトが森を切り開くことによってインフルエンザなどが持ち込まれてしまうことが書かれていて,ヒトと自然の共存の難しさを知った.
【1/6(月) 内容】
2日目の最初は,日本モンキーセンターにて,動物の行動観察の方法についての講義を受けた後,「フォーカルサンプリング」という方法で,ボウシテナガザルとアビシニアコロブスの個体1体につき生徒2人で,30分間,30秒ごとに行動観察・記録を行いました.それらの結果を全体で共有し,単雄単雌型のボウシテナガザルと,単雄複雌型のアビシニアコロブスの行動の違いを検討しました.


午後からは針江生水の郷にて,川端(かばた)を見学しました.個人の川端や共同の川端を見たり,湧き水の飲み比べを行ったりしました.また,どのようにしてこのような環境が守られてきたかなどについて,ガイドの方からお話を聞きました.
【生徒の感想】
◆日本モンキーセンター
・学んだ観察の仕方を生物部のカラスバトの観察にも活かしていきたい
・サルの行動がそれぞれの個体同士の関係性に影響されていたことが,実際に30分観察をした結果からよくわかり,30分見るだけでもこれだけはっきりとわかるのだと驚いた.
・動物園で動物を見る時,動いていなかったら「動いてないな」で終わってしまうところを,30秒ごとに観察することで「休息」として捉えることができ,新しい視点ができた.
◆針江生水の郷
・川端を流れている水が近所の家の川端とも繋がっているため,近所の人のことを考えて油などを流さないこと,下流の人は上流の人たちのそのような思いやりを受け取って丁寧に川端を使うことなど,針江だけでなくこの世界の資源に対しても言える考え方があり,大切にしていきたいと思った.
・琵琶湖の周りの地域の中で針江のように川端を使える場所は他になく,針江は条件が沢山重なって恵まれている環境だということがわかった.
・今までは、鯉に対して水を汚くするイメージがあったので、水路を綺麗にしていると聞いて興味深かった
・針江の人々は,私たちよりも水回りへの危機感などが大きく異なると思ったので,水に関する言葉の使い方について違いがあるのか調査したいと思った.
・川端を作れる街は全国に他にも5か所ほどあるらしいが,現在にも続いてるのは針江だけで,文化を守っていく大切さを感じた
・琵琶湖が氾濫しない様にするために水位を減らすことで,ほとりの植生が失われてしまうことは,固有種の減少のみならず文化の衰退であることもわかり,難しい課題だと思った.
・この場所に来るまで,人が住む場所の近くを流れる水やそこに住む生物たちと共存しながら送る生活について知らなかったため,このような場所や生活について私たちは学び,伝えていかなければいけないと思った.


【1/7(火) 内容】
最終日は,万博記念公園にて太陽の塔を見学しました.その後,国立民族学博物館にて,各自決めたテーマに沿ってワークシートを記入しながら,展示を見て回りました.




【生徒の感想】
・同じ農業用の道具でも形などが地域によって違い,それぞれの地域で工夫してきたこと
がわかって面白かった.
・食べ物は人と人を繋ぐ,神様と人を繋ぐなど,繋ぎの役割があることがわかったが,一方で食べなかったら土地から排除するなど,分離させる役割もあるとわかった.
・民族衣装はその土地や地域の気候や宗教などに合わせて布の面積が違うなど,土地の文化か反映されていて,民族衣装から土地の文化を考えるのが面白そうだと思った.
・ルーマニアのサンプツァ村には陽気な墓があるという展示があり,日本では墓のイメージが暗いものであるため,違いを感じた.また,陽気な墓は亡くなった住人1人に向けたもので,日本のように家族で共有しないところも違っていた.
・ヨーロッパのコーナーにはキャベツを千切りにするための道具があったが、現在使われているものと形があまり変わらず昔からあったことに驚いた.
・言語は自らをアピールするため,所属しているところを示すためのアイデンティティになるのではないかと感じた.
・貝の展示を中心に見ていて,二枚貝などは貝殻が薄いため,実用的な道具に使われる傾向があった.一方で巻貝は形が変わっているため装飾に使われているなどの違いがあった.
・イスラム教の文化の中にも,日本の書道のような文化があり,日本は字の持っている美しさを表現しようという考えがあるが,イスラム教にも同じような考え方があった.ただ,イスラム教は日本と違ってカラフルで,イスラム教のコーランに字の美しさや色についての記述があった.
・先進国が頭を悩ませている,後進国への格差解消のための支援策を計画する際も,相手国の文化を知ることは大切なことであるため,国立民族学博物館のような「各国の文化・民族性」を記録,保存,研究する場所は重要だと感じた.