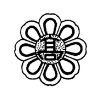ニュース
「社会人による講演会」
社会科学的思考力
――『見えないもの』を見るための道具を手に入れる

以下は、一年生探究係によるレポートです。
10月30日「総合的な探究の時間」の時間で2年生とともに一橋大学大学院社会学研究科教授の太田美幸先生のお話を聞きました。
主に社会科学について、大学の社会学部1年生の必修科目で話している内容をもとに、社会学/社会科学の面白さと有用性をお話しいただきました。


聞く前は社会には「見えるもの」と「見えないもの」だけだと思っていました。しかし、この二つにプラス「見えていないもの」という存在があることを聞いて驚きました。
推理小説の面白さと社会科学の面白さにはどちらも「意外なほど、面白い」という特徴があります。この意外性は「見えないもの」「見えていないもの」が見えることによって生まれます。そして、このことが地動説のように「ものの見方」を変え、常識を変え、社会制度さえも変える契機をつくることを知ったことで自分自身の世界に対する見方が変わりました。
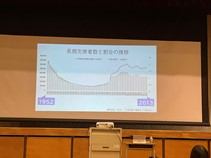
例えば、「不登校の子どもが年々増えている」と言われていたが、時代を遡って長期的にみれば実は増えているわけではなく、昔の状況に戻っていると解釈することができる。これがいわゆる「見えていなかったこと」にあたるという話はとても印象に残りました。
更に、読書は知識や情報を得ることが目的だけだと思っていました。ものの見方を鍛えるための読書即ち、「見えないもの」を見るための道具でもあると知りました。「読書」について。これは二通りの読み方があるそうです。
1 知識や情報を得るための読書(本を読むことで知識が広がる)
2 ものの見方を鍛えるための読書(世界が広がる)
「見えないもの」を見るのが社会科学という学問で、それを見るために、ものの見方を鍛えるための読書をすることが大切だと教わりました。今「見えているもの」だけでなく、見る領域を広くしたら、見え方が変わり、逆に狭くしても見え方は変わるそうです。今後は、読み終えた後に新しい見方ができるように読書をしようと思います。 探究係 白井・佐藤
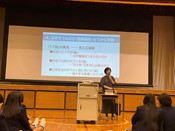
今回も講演会の運営は一年生各クラスの探究係が担いましたが、司会進行は、グループ探究で「ジェンダー」をテーマに社会科学ぶんやを学ぶ2年生が担当しました。
また、放課後、図書室にて大田先生とアフタートークの時間を設定し、多くのぶんじ生が集い、大学での研究や、大学生活について質疑応答があり、最後まで活発なやりとりがありました。 文責 探究部齋藤