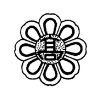ニュース
6月19日(水) 研究者や大学の先生をお招きして、専門分野の講話を聴く機会が設定されました。
その後の生徒によるフィードバックをご紹介します。
こうしたコメント一つを見ても、国分寺生のアカデミックな素養やポテンシャルの高さがうかがえます。

文学分野
- 昔の資料等は加筆がある場合を考えて鵜呑みにしてはいけない
- 今まで源氏物語は紫式部が書いた54巻だけだと思っていたけど源氏物語のファンが書いた今で言う同人誌のようなものもあると知り、日本人は今も昔も変わらないなと思った
- 文学部なんて考えたことも祝野にも入れたことがなかったけおもしろさの方が増し学んでみたいとも思った。
医療看護分野
- 児童虐待は、乳児が多く、また、母親が加害者であることが多いことが衝撃だった。
- 看護師は病院で働くことしか知らなかったが、海外で働いたり、企業することもできることを知ってとても驚いた。
- 国際看護というものがあることを知らなかったので、日本だけでなく、海外と関われる仕事でもあるとわかった。
医療工学 メカトロニクス分野
- xyz方向だけでなくそこに捻りを加えることで動きの自由度が上がること。
- 様々な知識を持っていないとアイデアは生まれてこないのでたくさんのものに興味を持つ。これからの人生を豊かに生きていくために大切なことだと思った。
- へその穴は思った以上に広がること。発想の転換から今まで関節部には3本のワイヤーが必要だと思われていたところを、2本に軽減できたこと。
- 研究はどんな感じなのか全く想像つかなかったけど、講師の先生が仰ってたようにどんどん何を作りたいから企業に自ら行って相談したり、そんな地道な工程があったということ。
心理学分野
- 心理学はただ感情を分析するだけでなく、それを会社の売上や製品の向上に活かすことが出来るという話が印象に残っている。
- 瞬間記憶のように単語を覚えて書き出すデモで、段段を階段と書いたこと。上下移動に関する言葉ばかりで々の字も使われていたから先入観が働き、違和感も持てなかったところが面白かった。
- 人間の記憶は確実ではなく、思い込みによる勘違いも多い。また、心理学は様々な分野にもつなげていくことができて興味深かった。
ゲノム情報分野
-
テストのとき、緊張すると問題が余計解けなくなるのは本当で、「どうしよう」という気持ちに頭を使ってしまっているから問題に使う注意力がなくなってしまっているのだそう。これからは不安な気持ちがあっても落ち着いていようと思った。日常生活に生かせる話があって、ためになった。
- 15個の単語を一定に出していき、どれだけ覚えているかというデモンストレーションをしたときに、本当は入っていない単語(似ている・その他の単語から連想されそうな単語)も覚えてしまっている人が多数いて、凄く面白いと思った。私自身もなぜか覚えていたので、騙された感覚で驚いたのと同時に不思議な気持ちになりました。
- CGに対してZAPが働くために、ウイルスの繁殖を防ぐことが出来るが、体の中では場所によってZAPのある量が違ってきていて、外のものによく触れる消化器などには多くZAPがあり、逆に心臓などにはほぼない、という内容がおもしろかった。
- 一本鎖RNAウイルスゲノムはCGが少ないからZAPがくっつけなくて、体内で生き残れるというお話が心に残った。
データサイエンス分野
- 統計学によって観光地の混雑予想や犯罪者の拠点などの特定もできるということにとても驚き、印象に残った。
- データサイエンスを用いた研究の事例は、今後役に立ちそうなものばかりで、予測の的中率も高くて印象に残った。
- 分析したデータを使って色々なことを予測できるのがすごいと思った。そのデータを使って自分で考える事が大事だと思った。
- 売り上げなどの比較的身近なものから、スポーツのデータの分析や犯罪心理の傾向の分析もできる
会計学分野
- 投資の仕方で長期的な投資と短期的な投資がありどっちが自分に合ってるか考えさせられた
- 多数派というのは一見従うべきなように見えるが、自分の首を絞めることに繋がるので、答えを急がず、考え続けるということが大切であるということ。
宗教学
- 強要しなければならない社会は生きづらい。
- 他者と対話して学ぶことが大切。
- 日本人は宗教について寛容だけれど、キリスト教やイスラム教、仏教、神道などの有名な宗教以外の新宗教は否定の意識がある。
- 私は新興宗教だけじゃなくて、宗教を信じてる人がちょっと怖いなってイメージがある。宗教勧誘とか盲目的な信者とかのイメージが強いから。こう思うのは日本が無宗教だからで、その影響の一環なんだろうなと思った。それか、外国は勧誘が無いのかもしれない。それこそ勧誘自体が無宗教の日本特有なのかも。
- 先生が最後におっしゃっていた【⠀郷に入っては郷に従え 】という言葉が印象に残っていて空気を読んで過ごすのではなく、自分で生きることが大切だとわかり、英語コミュニケーションの授業でやったrowコンテクストがやはり大事なのだとわかりました。
法学分野
- 自然法という考えと生きる法という考え。法律として紙に書かれているものだけでではなくて日常生活でのルールの大切さ
- "生ける法と法意識と国家制定法の違い
- 法律を学ぶ意味や誰が学ぶべきなのかと言うことについての話。法学部というと弁護士になりたい人が入る学部だと思っていたが、国民主権なのだから全員が法律を学ぶ意味があるということがわかった。
- 法学に対しての見解の違いの面白さ。
- 法学は大きく分けると二分野あるということを初めて知った。また、授業では実際の裁判についての文章を読んで話し合いをしたりするという話を聞き、法学部で学ぶことへの関心が高まった。
- 日本人が宗教だけではなく、馴染みのないものに対して嫌悪感を持つのはそう言う文化だからではないのかなと思った。そう言うものを排除しようとするのではなく、自分の見聞を広めて、いろんなことを知って、寛容になれればなと思った。それが僕らにできる、これからの日本の在り方だと思う。
教育学分野
- 教育には答えがないという言葉です。
- 西ヨーロッパは東アジアのみんなの模範となる先生像を重視するのではなくあくまで授業内容を教える仕事であるという意識の違い
- 東アジアと西ヨーロッパ、教師とteacherはどう違うのか、という話題でteacherは学びを教えるプロであるのに対し、教師はただ教えるだけでなく人格なども子供の手本となること。
- 採用試験を簡単にすれば多くの人が先生になるのではないかと考えていたけど、簡単にして良い先生がいなくなってしまったら日本の教育が悪くなってしまうのかなと思った。
- 教員志望者が減少しているのには理由があると感じた(主に業務の忙しさや、不相応のお給料)
- 生徒の視点ではなく教員の目線から研究なさっていて興味深かった。今の熱いトピックだと感じた。
- 教師は人生のお手本になるという話
- 「ヨーロッパではこうやっているから、日本も見習うべき」というのは必ずしも正当な意見ではない、ということ。
- 外国の教育実習生の服装や退勤時間などが日本と大きく異なっていたところ。
半導体分野
- スピン(電子も自転している)地球と太陽の関係のように、原子核と電子の関係も類似している
- ユニバーサルデザインや点字を見直して視覚障害者にとってより分かりやすいものを開発しようとしているという話を聞いたとき
- 電子というとても小さな存在を利用して、技術を作るということに驚きました。
ユニバーサルデザイン分野
- 身の回りの些細なものにも人間工学が使われていると知って科学の偉大さを知れた。細かいデータなどをとることが気の遠くなる作業だなと思った。
- 視覚障がい者の9割が点字を読めないという話を聞いて驚いた。カタカナをそのまま立体にするアイデアはとてもいいと思った。
- 筋肉に流れる電気を測ってどれくらいの負担がかかっているかを計測すること。
- 「使いやすさ」を数値化できるのが人間工学のすごいところだと思いました。目には盲点があることや年齢による有毛細胞の減少をデモンストレーションを通して体感することができて面白かったです。
- 文房具など、身近に使うものを使いやすいようにデザインするの楽しそうだと思った。
- 視覚情報を脳で補っている部分があったり赤の色を制御するために緑を認識する細胞が働いたりなど実際に体験できて、そういう事だったのかと納得した。
数学分野
- 1つの公式に異なる単位が関係をもっているのが神秘的」という考え方を聞いたとき、いつも使ってるだけの公式をそんな捉え方して神秘的なんて思うことがなかったからすごく印象に残った。
- オイラーの公式を最も美しい数式として生き生きと話していたところ
- 数学と美意識がつながっていること
薬学分野
- 薬学部は病院や薬局で働くだけでなく、行政機関や企業など幅広く活用できる仕事につける学部である
- 心拍数をある程度は自分の気持ちで下げることができるというはなし。また、「今日治らなかった病気が明日1粒の薬を作ることで明後日治る病気になる」という言葉。
- 今回の講演では、薬学の発達により障害や生まれながらに持つ先天的な病気が治ろうとしているという話がとても印象的だった。いままでは、このような先天的な病気たちの治療に関しては治療に限界があると思っていたものの、薬学の発展が今後に希望を与えてくれるという事実に驚愕した。
- 薬学部は薬剤師を目指すだけじゃなく、他にも様々な職業があり、選択肢が多いから、自分の進路をはいってから決めるのありだと言うこと。
- 私は食品会社で働くことに興味があるので、薬学部という選択肢もあるのだと知られて良い機会になったと感じました。
- 麻薬取締官や厚労省など、薬学部が活躍出来る場所が思っていたよりも多く、薬学部にさらに興味が湧きました。また、研究内容を伺って、具体的に研究がどんなことをするのかが分かったり、研究の面白さを知ることができ、私にとって良い経験になりました。