
本日、「Tokyoサイエンスフェア 研究発表会及び表彰式」が東京ビッグサイト国際会議場で開催されました。本校からは「科学の甲子園 東京都大会(11月14日開催)」に出場した4年生2名が参加し、5年生1名がポスター発表(展示)を行いました。
会場には64本のポスターが展示され、様々な研究に触れる良い機会となりました。また、高校生による英語でのプレゼンテーション発表や、東邦大学の風呂田利夫 名誉教授による講演など盛りだくさんで、多くの学びがありました。さらに「第11回 科学の甲子園 東京都大会」の結果が発表され、表彰式もありました。本校は総合成績で第3位(都立学校では第1位)に入賞し、生徒たちは大いに喜んでいました。
|
|
|
|
|
|
||
本校に大林組の方々をお招きして、11月12日(金)午後には1年生を、26日(金)午後には3年生を対象とした「テクノロジーセミナー」を実施しました。本年度は密集状態を避けるため、学年を多目的室と小ホールの2会場に分け、それぞれの会場で2クラスずつが受講しました。
講演では、建設業の紹介をはじめ、ダム・タワークレーン・宇宙エレベーター・木造建築等といったものの技術面についての話がありました。また、VRを利用して崖にある足場を経験したり、資材搬送システムでリモコンでブロックを運ぶ体験をしたり、タブレットを利用して高層の木造建築物の内部の3D体験をしたり、様々な体験学習も実施しました。
普段の学校での学習では経験できない様々な技術に関する話には、多くの生徒が興味をもって聞いていました。今回は学年全体での実施でしたが、本校では、希望者を対象とした講演会も数多く実施しています。ぜひ自分から積極的に参加して欲しいと思います。
|
|
|
|
本日の放課後、今年度3回目のWWL STEAM教育講座を開催しました。
今回は東京工科大学 コンピュータサイエンス学部の生野壮一郎 教授をお招きして「コンピュータ・スマートフォン・ゲーム機器、本当の実力」をテーマに講義していただきました。講義の最初では、スーパーコンピュータの処理速度の話題から、コンピュータの速さは何で決まるかをお話いただきました。コンピュータの速度をiPhoneやPlayStation、Nintendo Switch等と比較して、現在のスマートフォンやゲーム機器がいかに高性能であるかを説明していただきました。そして、コンピュータの心臓部である CPU の仕組みや性能、高解像度の映像に不可欠な GPU のお話をいただきました。
続いて、冒頭のスーパーコンピュータの処理速度は何で決まるかの秘密が明かされ、それは「連立1次方程式」を解くスピードだと説明されました。「n次元の連立1次方程式」の演算回数ということから、身近な場面における「連立1次方程式」の例や数学の大切さをお話いただきました。
最後に未来世代の生徒たちに、ソフトウエア開発を担って欲しい、数学はコンピュータサイエンスには不可欠で論理的思考力が養われること、英語で書かれた論文を読む必要から英語をしっかり学習するようにというメッセージをいただきました。中学生には難しい内容もありましたが、参加した生徒たちはしっかりと講義を聞き、講演後、質問もしていました。
|
|
|
||
|
|
|
以下に生徒の感想を紹介します。
本日の1・2時間目、本校体育館において、3年生のレシテーションコンテストの本選が行われました。10月末の予選を通過した13名の生徒が、約300語からなる英語のスピーチを暗唱し、たくさんの生徒の前で発表しました。
壇上の発表者は、身振り手振りを交えながら、練習の成果を堂々と発揮し、発音や、間の取り方、表現力など、ハイレベルなコンテストとなりました。かなり広い空間に、発表者の熱のこもった声が響き渡り、耳を傾ける生徒たちも引き込まれていました。
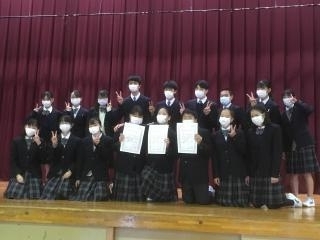
3年生は、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が共催で募集をした ”中学生の「税のついての作文」” に応募しました。そのうち、4名が入賞しました。「税についての作文」とは、将来を担う中学生の皆さんが、身近に感じた税に関すること、学校で学んだ税に関すること、テレビや新聞などで知った税の話などを題材とした作文を書くことで、税について関心を持ち、正しい理解を深めていただくという趣旨で実施しているものです。
本日、JR八王子駅前にある八王子市学園都市センターにて、入賞者4名(うち1名は欠席)の表彰式が行われました。本校生徒が受賞した賞は、以下の通りになります。おめでとうございます。
| 東京納税貯蓄組合総連合会会長賞 | 1名 |
| 八王子税務署長賞 | 1名 |
| 八王子商工会議所 会頭賞 | 1名 |
| 東京税理士会 八王子支部長賞 | 1名 |
|
|
|
本日の放課後、今年度2回目のWWL STEAM教育講座を開催しました。
今回は東京工科大学 デザイン学部の伊藤英高 准教授をお招きして「アート ~ 映像表現:その歴史とデジタル技術の可能性」という講座を実施しました。講義の冒頭では、現在の環境の中の映像、NETFLIX、YouTube、TikTok、スマホやSNSでの映像発信、街中にあるデジタルサイネージなどの現状を説明いただきました。その後、映像の歴史を振り返りました。炎や太陽による影も映像であることから始まり、カメラ映像、20世紀に入ってからの映画の誕生、映画技術の進歩、デジタルによる画像処理までを学びました。生徒たちにとっては初期の映画の映像が新鮮に感じたようです。
講義の後半では、現代では「動画」がコミュニケーションツールになっているという視点から、様々な映像技術を紹介していただきました。最後に、大学生が作成した映像を見ながら、映像の可能性について説明していただきました。また、映像を学ぶ上でもHTMLやpythonなどのプログラミングを学ぶ大切さもお話いただきました。
|
|
|
||
|
|
|
以下に生徒の感想を紹介します。
本日、「Tokyoサイエンスフェア 第11回科学の甲子園 東京都大会」が都立小石川中等教育学校で開催されました。本校からは、5年生3名、4年生3名の生徒が参加しました。
大会は筆記競技と実技競技で競います。筆記競技は、2時間で物理・化学・生物・地学・数学・情報に関する問題にチーム全員で取り組みました。実技競技は、事前にテーマが公開されていて、与えられたプラスチック製の箱を用いて、中身の構造を工夫し、箱Aと箱Bを制作します。作成したそれぞれの箱を斜面に置き、斜面の角度を大きくしていきます。箱Aは倒れやすさを競い、箱Bは倒れにくさを競う競技でした。これまで校内で検討してきた設計図やメモを持ち込んで取り組みました。参加した生徒からは、「問題は難しかったけど、仲間と相談しながら取り組んで、とても面白かった。」という感想がありました。
本日の結果は、11月28日(日)に開催される「研究発表会及び表彰式」で発表されます。良い結果であることを祈っています。
|
|
|
日本文化部(書道)では、東京芸術劇場ギャラリー1・2で開催された「第34回 東京都高等学校文化連盟 書道展」に作品を応募しました。その結果、見事に「推薦賞」を受賞しました。本展の審査員をしている複数の大学の先生方から高い評価を受けての受賞となりました。
これまでも様々な書道展等で受賞している生徒ですが、「自分の作品が評価されて嬉しい。」と受賞の喜びを話してくれました。
|
|
|
本日、3年生は「第2回科学調査」に取り組みました。これはフィールドワーク活動で実施している「科学的検証活動」の中心に位置付けられているもので、1日かけて自分たちの班のテーマに応じた調査や実験等を行いました。昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で1回しかできませんでしたが、今年度は感染症対策に配慮しながら、例年のように2回目を実施することができました。
7月8日の第1回に引き続き、校内の教室や実験室、体育館等や、校外の浅川の堤防を使って活動を行いました。どの班も今までの活動をもとに、よりテーマを深めたり、関連した内容に挑戦しました。
今後、今までの活動をまとめ、来年3月に予定されている成果発表会で発表する予定です。
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
本日、3年生が東京都立大学南大沢キャンパスを訪問しました。この訪問は、進路意識を高めることを目的として、毎年11月に3年生を対象に実施しています。今年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、学年全体を午前と午後という二つのグループに分けての訪問となりました。
東京都立大学のキャンパスでは、高大連携室長の河西奈保子教授と大学院生の講演を聴きました。また、3年生がフィールドワーク活動で実施している「科学的検証活動」に関して、各クラスから一つの班が発表を行いました。中学生が大学の先生方や大学院生の前で発表できるのは貴重な機会です。いずれの班も、高大連携室の方々からの質疑応答やアドバイスを受けることができました。
河西先生からは、本校での日々の授業の大切さ、とりわけ本校のフィールドワーク活動の意義についてのお話がありました。各生徒が現在の学校生活と将来とのつながりを見つけ、大学の雰囲気に触れるのに絶好の機会となったと思います。
|
|
|
|
2年生は、先週の10月29日(金)から2週にわたって「総合的な学習の時間」で発表を行いました。
「モノ語り」とは、人が作ったモノについて様々な視点で探究する活動です。班ごとに対象となるモノを決め、文献調査やアンケートを取るなど、自分たちで調査を行います。さらに、企業の方にオンラインやFAXなどで質問も行ってきました。どの班も苦労しながらまとめたのです。
今回は3月の成果発表会に向けての中間となる発表でした。調べてまとめた結果を演劇で発表する班や、クイズ形式で発表する班などもあり、工夫して取り組んでいました。まだまだ調べ足りていないこともありましたが、これから内容をもっと掘り下げ、本番に向けてさらにより良いものにして欲しいです。
期待しています、2年生!
|
|
|
 東京都立南多摩中等教育学校 Tokyo Metropolitan Minamitama Secondary Education School
東京都立南多摩中等教育学校 Tokyo Metropolitan Minamitama Secondary Education School