令和1年度高大連携事業 「大学分野別模擬講義」
「大学より講師を招き、生徒が現時点で興味・関心を持つ専門分野の講義を受講することで、
各々の進路に対する意識を高める」という趣旨で、2学年全生徒を対象に10月29日(火)に、
14:05から16:05にかけて大学分野別模擬講義を実施しました。
 |
 |
| 一橋大学 柳 武史 先生 |
慶応義塾大学 藤田 康範 先生 |
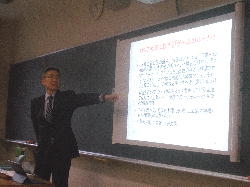 |
 |
| 東京外国語大学鈴木 義一 先生 |
早稲田大学 小沼 純一 先生 |
 |
 |
| 東京学芸大学 大森 直樹先生 |
東京大学 島 亜衣 先生 |
 |
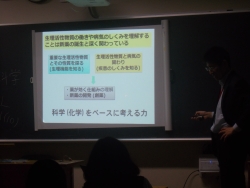 |
| 東京工業大学 竹村 次朗 先生 |
東京薬科大学 田村 和広 先生 |
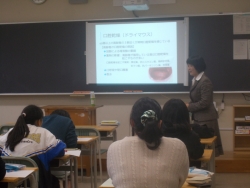 |
|
| 千葉大学 岡田 忍 先生 |
|
ご参加いただいた大学、学部、講師、演題、並びに受講者の感想を以下に紹介します。
(講義番号順に記載)
1.一橋大学(法学)柳 武史准教授
演題:「独占禁止法の役割と法学部での学びの意義)」
・「法律」というと解釈が固定されたルールのように考えていたが、実際には様々な
解釈ができるという事を学んだ。
・法学部では、人を説得するための表現力、プレゼンテーション能力も身につく。政
治学や、国際関係等も幅広く学べ、将来は法律関係以外にも、様々な職業につながる。
2.慶応義塾大学(経済学)藤田 康範教授
演題:「自我昨古」の経済学―イノベーション・感動の設計・戦略の経済分析に向けて
・今のままの日本では、2050年にはGDPがインドにも追い抜かれ、先進国としてとど
まることもむずかしく、国際社会でのプレゼンスが低下するというお話を伺って、危
機感を抱いた。
・経済学=お金に関する“シビアな学問”というイメージを抱いていたが、先生のお話が
面白く、経済学を身近なものと感じることが出来た。
3.東京外国語大学(総合国際学研究院)鈴木 義一教授
演題:「ロシアの論理」を考えてみる:地域研究の課題と方法
・ロシアの多極主義:超大国アメリカの一極集中の世界であってはならない。対立を
望むわけではないが、ロシアも、一極の担い手となりたい。立場が違えば、一つ事に
対して、様々な見方があると学んだ。
・日本人の多くは、ロシアに対して良い印象を抱いていないが、ロシア人は日本に対
して好印象を抱き、身近な存在と感じているというお話に驚いた。
4.早稲田大学(文化構想学部)文芸・ジャーナリズム論系 小沼 純一教授
演題:「声・言葉/音・音楽」
・「表現」という言葉が深いなと思った。自分の持っているものを表すだけでなく、
それを聞き取る繊細さが必要というのが興味深かった。
・言葉を音声から考えたり、語源から考えたりすると、見え方が大きく変わるこ
とに気付かされた。また、文学と音楽にこれほどまで密接な関わりがあるとは思っていなかった。
5.東京学芸大学(教育学)大森 直樹准教授
演題:「教育の意味はだれが発見してきたかー教育実践記録から」
・教授法に重点を置いた講義になると思っていたが、それ以上に大切なのは、どの
ように生徒とふれあい、理解してあげられるか、なのだという事を学んだ。
・講義の後半を本校卒業生で学芸大4年生の持田朗生先輩が引き継がれたが、NHK
の朝ドラ「陽だまり」のワンシーンを見せてくださった。その中での陽子先生の相
手への言葉がけ、接し方に感銘を受けた。私も、まずゲームをやりすぎる弟への言
葉がけに工夫をこらそうと思った。
6.東京大学(生物学)情報理工学系研究科 島 亜衣特任助教
演題:「大学で学ぶ細胞とDNA」
・細胞を「使って」、匂いを感知できる機械を作ったり、人間にはできないことを
してみたり、ひいては動物実験の代用をさせたりと、細胞の使い道は様々あると知
った。素晴らしいことだ。
・お話を伺って、東大へ行きたいと思った。専門を決めるときには、研究室などに
ついても調べてみたいと思う。
7.東京工業大学(土木・環境工学系)竹村 次朗准教授
演題:「インフラ・都市開発―効用とリスク」
・東京湾の埋め立て地は、ただ単にゴミの廃棄場だと思っていたが、湾に注ぎ込む
川の流れにも配慮して埋め立てが行われている事、災害時には、ガレキ処理にも利
用されていることなど、新たな一面を知った。今後の埋め立て地の有効活用法など
についても知りたいと思った。
・都市開発、工事を行う際に、障害となるのは、技術不足だけだと思っていたが、
利害関係者の思惑なども絡み、もっと複雑なのだという事が分かった。都市インフ
ラの安全・安心を、万人に納得させることの難しさもひしひしと感じられた。
8.東京薬科大学(薬学)田村 和広教授
演題:「薬の作用と良薬」
・薬には効能もあるが、副作用もあること、また、薬の大部分は、病気の原因を
除去することはできず、症状を改善するものだという事が分かった。
・英語力(文献を読む際に必要)と有機化学への理解が非常に重要だという事が分
かった。想像以上に進路の選択肢が多いようだ。
9.千葉大学(看護学)岡田 忍教授
演題:「口から食べることの意義」
・口腔機能の衰えは、栄養摂取の低下ばかりでなく、糖尿病、動脈硬化、認知症
とも深くかかわっており、誤嚥性肺炎の原因ともなり、高齢者の健康と大きくか
かわるものだという事を知った。
・看護士は、直接、医療的な治療にはあたれないけれど、患者を支え、病気を治
していくうえで、とても重要な役割を担っているという事を認識し、改めて職業
としての魅力を感じた。
講義当日は、資料印刷のために朝早くからいらして印刷を済ませ、大学での講義
を終えて、再度講義のために本校へ赴いてくださった先生、地方への出張が入って、
途中講義を抜けるため、在校生(本校卒業生)を伴って大学生活紹介、並びに受験対
策指導は学生に任せて、出かけられた先生と、講師の先生方は、それぞれ無理を押
して、本校生徒のためにご講演くださいました。心より感謝申しあげます。


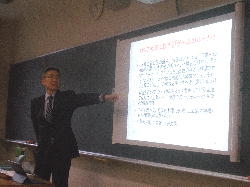




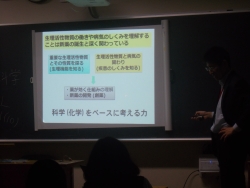
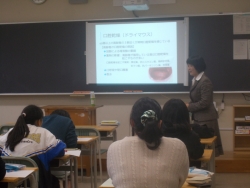
 東京都立新宿高等学校
東京都立新宿高等学校