東京理科大学で物理実験を体験しました。
8月27日(火)、本校生徒8名(5年生5名、4年生3名)で、東京理科大学の御協力の下、大学1年生の授業で行われているものと同様の物理実験を体験しました。
実験内容は、前期課程(中学校相当)の学習内容である「慣性の法則」と「作用・反作用の法則」を確かめるものです。以下の3つの実験を行いました。
1 慣性の法則を確かめる実験
<実験手順>
(1)大きな台車の上に小さな試走車を乗せる。
(2)台車をおもりと糸でつなぎ、おもりの重さで加速させる。このとき、試走車と台車は同時に運動する。
(3)下の台車を壁に当てて停止させる。上の試走車は慣性の法則に従うため、前に進み続ける。
(4)このときの停止する直前の台車の速さをV
1、台車が停止した直後の試走車の速さをV
2として記録をとる。
(5)おもりの重さを変えてV
1、V
2を計測し、横軸V
1、縦軸V
2のグラフにプロットする。
(6)V
2/V
1を求めて、その理由を考察する。


2 慣性の法則を用いて考察する実験
「だるま落とし」を物理的に考察する。
・上に乗っているものの個数の多い方がやりやすいのか、それとも少ない方がやりやすいのか。
・どのようにハンマーを当てれば、まっすぐ落ちるのか。
このような問いを教授の方々に立ててもらい、繰り返し実験を行い、考察する。

3 作用・反作用の法則を確かめる実験
<実験手順>
(1)2つの押しばねはかり同士を合わせ、片方を押す。
(2)押す方のばねはかりの値をF1、押される方のばねはかりの値をF
2として記録をとる。
(3)横軸F
1、縦軸F
2のグラフに記録をプロットし、F
2/F
1を求めて、その理由を考察する。
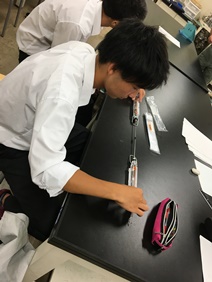
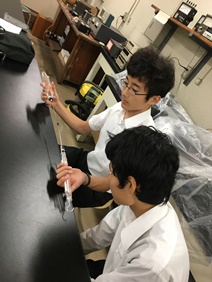
理論値と実験値が異なる理由を考察することで、物理現象のより深い意味を理解することができました。実験者の科学的な思考のプロセスや問いの立て方を学び、今後の科学の学習やステージ論文の作成に生かすことができそうです。
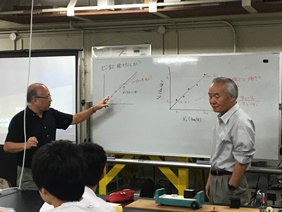
講義を受けている様子



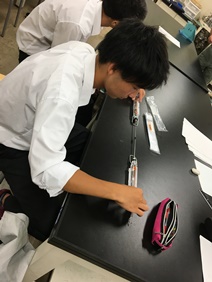
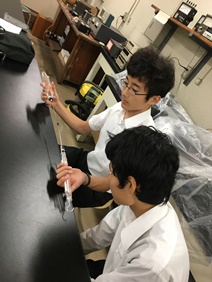
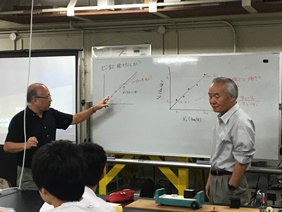
 東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School
東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School