本校で実施している進路行事の一部を紹介します
勉強合宿
日程:2泊3日
対象:2年生希望者
目的:受験生になるための意識の切り替え、自学自習の学習習慣の確立
概要:参加者は3~4程度の講座を取り、それ以外の時間は講習の予習・復習、または各自で課題を決めて勉強に取り組む。
約48 時間の滞在期間中、「24 時間以上」の学習を目標に、各自が「自分へのチャレンジ」を行う。
熱心に学習に取り組む仲間に刺激され、参加者の多くが「勉強浸け」になります。
過去の参加者の平均学習時間は23.5 時間、最高は29 時間という年もありました。
「留学生は先生」
対象は1学年全員。進路志望の高い志を持ってもらうことや国際理解・国際交流を目的として、毎年行っている行事です。留学生の方々に、それぞれの国の紹介や進路を選んだ理由などの世界観の広がるお話を聞きます

「社会人によるキャリアガイダンス」
対象は1学年全員、進路目標を持ってもらうために1年間で全17講座が定期試験の後や土曜日に実施されます。生徒は興味を持ったテーマ上を選んで、お話を聞くことができます。各会場では、それぞれの講師の職業に関するお話や進路決定に関する助言をもらいます。
「大学見学会」
対象は2年生、7月の期末考査終了後に、毎年大学見学会を実施しています。首都圏の国公立大学を中心に10大学12コースに分かれて大学を見学します。内容は、各大学の説明、大学(院)生との交流、体験授業などです。第一志望校を決めるための第一ステップで、国公立大学のよさを体感してもらうのが目的です。
進路講演会「脳を知り脳を生かす」
対象は1,2年生の生徒全員とその保護者(希望者)体育館にて実施しました。講師の池谷裕二先生は、東京大学大学院薬学系研究科准教授で、神経回路学、グリア生理学、システム薬理学がご専門です。研究以外に、たくさんの著作や講演によって、最新の脳科学の成果を広く発信されています。 著書には、受験脳の作り方~脳科学で考える効率的学習法~、記憶力を強くするなど多数があり、どれも大変魅力的です。
<講演の概要>
- 海馬とは。:学習内容を一時的に蓄える。その間に記憶すべき対象の選択をする場である。しかし、1ヶ月たつと短期記憶は完全に失われるため、その前に復習して長期記憶に移行させるべき。
- 記憶の実体は?:ニューロンが作る複雑な回路の中で、どこをどのように信号が通過するかが記憶の内容となる。記憶した状態では、信号がその回路を通りやすくなる。
- 復習の重要性:復習は、忘れる速度を遅くしてくれる。
- 記憶の選択の基準は?:従来は、何度も覚えようとすることで記憶が定着すると考えられていたが、現在は、記憶した内容を出力することのほうが重要だとわかった。つまり、脳は使う頻度の高いものを記憶として残す。
- シータ波とは?:記憶の活動が活発なときに出る脳波の一種。これを指標として学習に適した条件を探ることができる。
- 歩いているとき、興味を持ったものの学習などでシーター波がたくさんでる。
- レミニッセンス現象:眠るとその間に記憶が整理されるため、テストの点がアップ。寝る前の1,2時間は記憶に最適。
- 分散学習vs.集中学習:分散学習の方が学習内容の定着率が高い。学習と学習の間に睡眠が入るため。
- 食事と記憶:胃が空っぽのときにグレリンというホルモンが胃から分泌され、それが間脳視床下部に影響を与え、空腹感が生じる。グレリンは、海馬にも影響を与えて、その活動を高める。したがって、食事前の学習が効果的。
- 脳と体の関係:表情と姿勢が感情を牽引する。体がスイッチになっていて、それによって感情が変化する。したがって、やる気が出ないときにもとりあえずやり始めると、後からそれに合った感情になってゆく。
- 笑いの伝染:笑ったときの表情をわざと作ることも効果があるが、笑っている人を見ても感情が変化する。



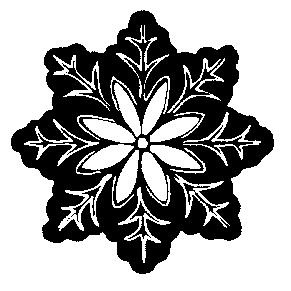 東京都立小山台高等学校
東京都立小山台高等学校